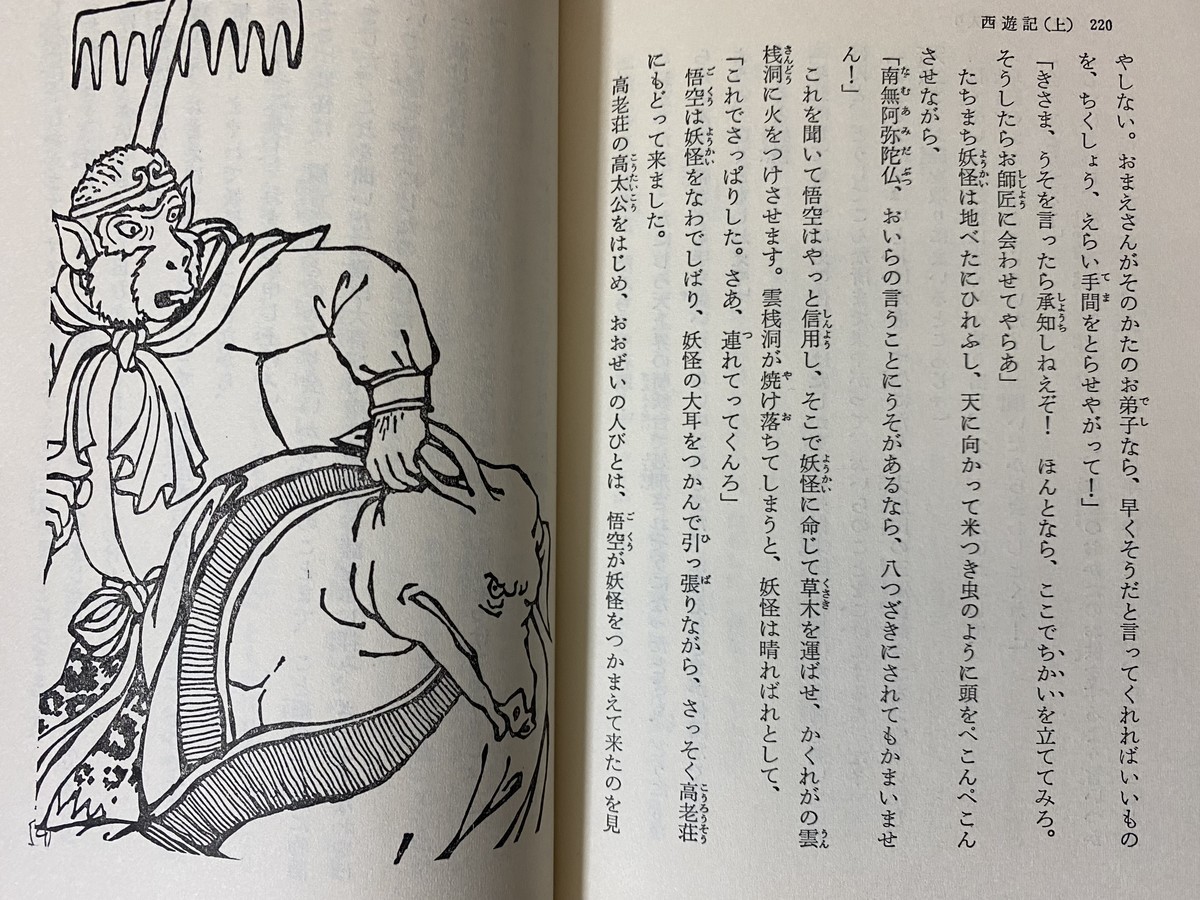「悪を断つのが魔界騎士ならば~。
わたしのポンコツ、なぜ断てぬ~。
花の刃をキラリとかざし~。
いつか咲かすぞ、ノマド華(ばな) ~」
ある日の夕暮れ、リーナは多魔川のほとりを自作の歌を口ずさみながら歩いていた。
久しぶりに地上に出ての帰り道だ。
今度、ちょっと長い夏休みをもらえることになって、魔界にいるアデルハイトの所に遊びに行く約束をしたので、そのお土産を買いに出かけたのだ。
初めて会った時、リーナが行動食として持っていたリンツのチョコレート「リンドール」を美味しい美味しいと喜んでいたので、表参道にある店まで行ってギフトボックスを買ってきたところだ。9種類50個も入っているので長く楽しめるだろう。もちろん自分用のも量り売りで適当に買ってきた。
あとは彼女の師匠であり、真の魔界騎士の試練ではリーナも大変世話になったベオウルフ様へのお土産だが、イングリッド様によると辛子明太子が大の好物だという。あれはあまり日持ちしないので、出かける間際になって冷蔵されているのを買うつもりだった。
夕暮れの多摩川には爽やかな風が吹いている。澄んだ水の香りがなんとも心地よく、リーナの歌声もいい感じに弾んだ。
多摩川の名の由来は魔界に一番近い街ヨミハラがすぐ近くにあるから――とかではなく、古来より霊力を持つ川として霊(タマ)から来ているとも、美しいものを意味する玉(タマ)から来ているとも言われている。
そんな万葉の昔から知られた川でリーナが歌声を響かせていると、いつか見たような光景が飛び込んできた。
「むむっ、また大きな犬がいるぞ」

丸子橋のたもとに遠目に見てもスケールがおかしい、遠近感が狂いそうな大きな犬が座っていた。
キラキラ光る銀色の毛並みで、その身体に鎖を巻いていて、前にリーナが海のラップ大会で鐘一つで落ち込んでいた時、この川で出会った大きな犬に似ている。
あの時は向こうも足を怪我してしょんぼりしていて、リーナのラップで励ましたらとても喜んでくれた。なかなか見上げた犬だった。
「あの時と同じ犬だろうか?」
大きな身体で岸にちょこんと座って、ぼんやり川を眺めている寂しげなポーズが以前の記憶と重なる。
また何かで落ち込んでいるのなら唯一の犬の友達として元気付けてやりたいが、あの犬かどうかちょっと自信がない。
大体、リーナは犬の顔の違いがよく分からない。苦手なので普段あまりちゃんと見ていないのだ。じっと見ようとするとなぜか吠えられる。吠える犬は怖い。吠えなくても怖い。
もしかしたら、あの時の大きな犬と良く似た別の大きな犬かもしれない。だったら近づきたくはない。
「うーん、どうしよう」
思い切って声をかけてみるか、見なかったことにするか迷っていたリーナだが、
「あっ、いいことを思いついたぞ」
あの時のラップをさりげなく口ずさんで遠くからゆっくり近づいてみよう。同じ犬だったらきっと気づいてくれるはずだ。気づかなかったら別の犬だ。
「ふっふっふ、我ながら素晴らしいアイデアだ。魔術師のエレーナでもきっと思いつかないだろうな」
自画自賛してから、もしあれが別の犬で、いきなり吠えかかられても大丈夫なようにしっかり距離をとって、いつもより少しだけ抑えた声で、『魔界騎士だぜヘイチェケラ!』を歌い始めた。
「ヨ、ヨー、魔界騎士、ヤバイ意思っ、嵐騎のパッション、本気のアクション――」
と、そこまでライムを刻んだところで、大きな犬がぴくっとこちらを振り返った。そして次の瞬間、
「わんわんわんわん!」
ものすごい大きな鳴き声と共にこちらに猛然と向かってきた。
「うわああああああ!」
思わず悲鳴をあげてしまう。
反射的に剣に手がかかったが、あの時と同じ人懐っこい顔になんとか抜くのを堪える。
果たして大きな犬はリーナのそばまでやってくると、その巨体を親しげに擦り付けてきた。ふさふさした銀色の毛からは、覚えのある不思議な匂いがした。同じ大きな犬だ。
「そ、そうか。やっぱりお前はあの時の犬だったんだな。久しぶりだな。しかしいきなりあんなダッシュは良くないぞ。お前はすごく大きいんだからな。普通は驚いてしまう。私は魔界騎士だから平気だけどな」
大きな犬をこわごわ撫でてやりながらリーナは言う。
「くーん」
大きな犬はその恐ろしい見かけとは裏腹に甘えた声を出した。
「今日はどうしたんだ。なんだかまた落ち込んでいたようだったぞ。悩みがあるならこの魔界騎士リーナが聞いてやろう」
そう言うと、大きな犬はまたくーんと鳴いて、首輪のあたりをモゾモゾとまさぐった。そしてそこに挟んでいたタブレットを取り出し、それをリーナの腕ほどもある大きな爪で器用に弄り始める。
「なんだ? 犬語の翻訳アプリか?」
大きな犬はふるふると首を振り、「ちょっとこれを見て」という感じで、一つの動画を再生させた。
現れたのは厳つい甲冑を身に纏った女戦士 たちだ。数が多い。10人以上いる。みんなカメラの方を見てざわついている。
「もう始まってるのか? それで録画とかいうのをしてるのか?」
「そのようだ。人間の機械はよく分からないが」
「おい、そんなに押すな」
「ここじゃ私が映らないかもしれないいだろう」
「そしたら私が見えなくなる。ダーリン! 見てる? 私、ジークリンデ」
「一人で先に挨拶するな。抜け駆けはなしと決めたはずだ」
「お前はいつもそうだ」
「今の罰としてそこをどけ」
「やれるものならやってみろ」
妙にかしましい女戦士たちはカメラに映る一番いい位置を争ってゴチャゴチャやり始めた。そしたらブツッと動画が切れ、またすぐに始まった。
今度はちゃんと並んでいる。カットされた位置決めのシーンで一悶着あったらしく、真ん中にいる戦士は嬉しそうで、端に追いやられた戦士はちょっと残念そうだったが、それでも全員で仲良く声を揃えて言った。
「ダーリン! 今日は私たち鬼神乙女(ワルキューレ)がダーリンのために開発した新しい技を見せますっ! 誰が一番すごかったか教えてねっ! お願い、ダーリンっ!」
女戦士たちの言葉にリーナは驚く。
「鬼神乙女(ワルキューレ)? 魔界の最果てに住むあの伝説の女戦士たちか? なんだかイメージと違うな」
そんな戸惑いをよそに鬼神乙女たちはそのダーリンのために開発した技とやらを披露し始めた。
「一番手は私、テューレだ。私の新しい技は『Anger of the wife(妻の怒り)』だ。だが勘違いするなよ。妻の私は勇者(エインフェリア)のお前に決して怒ったりしない。私たちの仲を引き裂こうとする悪しき者への怒りがあるのみだ。……あ、いや待て、伝説の夫婦喧嘩と言うものにはすごく憧れている。結婚したら是非やろう。……うるさいな。少しくらいダーリンに喋らせろ」
テューレというその鬼神乙女は「前置きが長い」という周りの声に文句を言ってから、剣をキリリと構えた。
「ダーリン! とくと見ろ! Anger of the wife!」
どかああああああん!
テューレが剣を振り下ろすと、天が割れたかと思うほどの雷が落ちてきた。画面が一瞬真っ白になり、それが晴れると地面に大穴が空いていて、あたりの空気がバチバチ鳴っている。すごい威力だ。
それを皮切りに、鬼神乙女たちは一人一人順番に技を披露し始めた。
あたり一面を灼熱の業火で包み込んだり、逆にそれを一瞬で凍結させたり、大竜巻や大津波を起こしたり、空間そのものを切り裂いたりと、伝説の鬼神乙女の名に違わぬ技を見せてくれたが、誰も彼もがそのついでに、交換日記に憧れてるだの、学校帰りに二人で寄り道したいだの、初めてのキスは観覧車の中がいいだの、夫婦でも隠し事を作ってみたいだの、はたまた嫁姑戦争を楽しみにしてるだのと変なことを言っている。
ともかく13人分のアピールが終わると、鬼神乙女たちはまた整列して、
「ダーリン! 早く私たちと子作りしようね! みんな待ってるからねー!」
満面の笑みで手を振って動画は終わった。
「なんなんだこれは?」
「くぅん?」
大きな犬は自分もよく分からないと言いたげに首を傾げた。
「要するにお前は彼女らが言ってるダーリンとやらに今の動画を届けるように頼まれたのだな?」
「わん」
「でもここでボンヤリしていたということは行きたくないのか?」
「ぐるるぅ」
大きな犬は低い声で唸ってから、ペタンと地面に伏せた。よくわからない仕草だが嫌がっているようだ。
「しかし主人のお使いはちゃんとやらないと駄目だろう。お前を信頼して託したのだからな。変なビデオメールだが」
リーナの正論に大きな犬は「でも嫌なんだもん」と言いたげに巨体をモゾモゾと揺すった。
「そんな大きな身体をしてしょうがない奴だな。チョコでも食べるか? 嫌な気分の時には甘い物だぞ。ん? 犬はチョコはダメなんだったか?」
さっき自分用に買ってきたリンツのリンドールを取り出しながら尋ねると、大きな犬は「平気平気」という顔で舌をハフハフさせた。
「そうか。お前もただの大きな犬ではなさそうだしな。チョコくらい食べるか。でも少しにしておけ」
「くーんくーん」
リーナが三つほど分けてやると、大きな犬は嬉しそうに喉を鳴らして、その身体からすれば豆粒よりも小さいチョコを一つ一つじっくり味わっている。違いのわかる犬だ。
リーナは自分もポイッと一つ口に入れた。ミルク味だ。とっても甘い。
「もぐもぐ。ひょっとしてあれか? ダーリンとかいう奴が苦手なのか?」
「わん」
大きな犬は頷いた。どうもそうらしい。
「あれだけの力を持つ鬼神乙女に好かれているのだ。よほどの力を持った男だろうな」
「ぐるる?」
大きな犬はそうかなあと言いたげにまた首を傾げる。
「そうでもないのか?」
「わん」
「そうか。ならばお前自身がそのダーリンと戦って、力を確かめてみたらどうだ。お前はただの大きな犬ではなく、鬼神乙女たちに仕えるひとかどの大きな犬のようだ。ならばその資格は十分にある」
「くうん?」
「私もアデルハイトという親友でライバルがいる。今度遊びに行くのだが、まずはひと勝負して互いの力を確かめるつもりだ。本気でぶつからなければ分からないことはある。ダーリンが苦手というお前の気持ちも変わるかもしれないぞ。主人のためにもその方がいいと私は思う」

大きな犬はしばらく考えていたが、やがて納得したらしく尻尾をぷるぷると振った。
「わんわんわん」
「そうかそうか。では迷いのなくなったお前のためにまた一つ歌ってやろう。聞きたいか?」
「わん!」
リーナは自分のスマホを操作してYouTubeから伴奏を流し始めた。
大きな犬はリズムに合わせて右に左に体を揺する。リーナは高らかに『魔界騎士ヨミハラ』を歌い出した。
「悪を断つのが魔界騎士ならば
わたしのポンコツなぜ断てぬ
花の刃をキラリとかざし
いつか咲かすぞ、ノマド華(ばな)
昨日闇討ち、明日は刺客
狙い狙われ、剣林弾雨(けんりんだんう)
なんの負けるな、桜のハート
今日もヨミハラ、嵐吹く
倒(こ)けつ、転(まろ)びつ、鍛えた力
かかげた剣(つるぎ)に、迷いなく
主人(あるじ)、ライバル、仲間がいれば
怖い野良犬、怖くない
夢に描くは、あの日の翼
斬るも歌うも、全力勝負
泣いて笑って、疾風(かぜ)より速く
いざや進まん、魔界騎士」
リーナが四番までしっかり歌い上げると、大きな犬はもうじっとしていられないという様子でブルブル身体を震わせ、夕日に向かって「わおーーーん」と見事な声を響かせた。野生の狼のようだ。
銀色の身体から勇猛果敢なオーラが溢れている。なにか感じとってくれたらしい。やはりこの大きな犬とは相通ずるものがある。
「よし行け! 大きな犬! 見事役目を果たすのだぞ! お前の行手に幸あれ!」
「わんっ!」
リーナがなんとなく夕日を指差すと、大きな犬は弾かれたように夕日に向かって駆け出したが、すぐに「おっと間違えた」という感じで右に方向転換し、風のように走り去っていった。
「そうか。ダーリンがいるのはそっちだったか。そういうこともあるな。ではまた会おう」
小さくなっていく大きな犬に手を振って、リーナもヨミハラに足を向ける。
「主人(あるじ)、ダーリン、仲間とともに〜、いざや進めや、大きな犬〜〜」
ちょっと歌詞を変えた歌声が夕暮れの多摩川をわりと適当に流れていった。
こうして、五車の対魔忍ふうま小太郎は、大きな犬フェンリルと『決戦』することになったのだった。
めでたしめでたし。
(了)
【制作後記】
またリーナとフェンリルの小話を作ってみた。
最近、いきなり決戦にフェンリルが登場したので、その理由をちょいと考えてみたかったのと、勝手に挿絵に使わせてもらった神尾96氏のフェンリルが可愛かったのと、チアルの話のときにリーナの歌を勢いで四番まで作ってしまったので、せっかくだから全部フェンリルに聞かせたかったからだ。
もちろん非公式の与太話だ。そもそも『決戦』なんて出来事は作中で起こってない。
『魔界騎士ヨミハラ』という曲名は、ヨミハラという名の魔界騎士がいるみたいで妙な感じだが、リンクにも張っている通り、元ネタが『侍ニッポン』という曲なので、それと字面を合わせたらこうなった。
徳山璉による1931年の歌だ。当時、10万枚も売れたヒット曲だそうだ。
さすがに知らない人がほとんどだろうが、アニメ『侍ジャイアンツ』で主人公の番場蛮が「球を打つのが野球屋ならば、あの子のハートがなぜ打てぬ」と替え歌を口ずさんでいたのを覚えている人はいるかもしれない。私もそっちが先だ。
歌より先に郡司次郎正による同名の小説があり、なんと5回も映画化されている。
その小説はAmazonで今でも普通に買えたが、映画で見ることができたのは5回目の監督:岡本喜八、主演:三船敏郎の『侍』だけだった。
同監督の『独立愚連隊』とかが好きな人はかなり楽しめると思う。
では、えらく久しぶりの更新となってしまったが、今回はこのへんで。